お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318
お問い合わせ・ご相談は
![]() 03-5803-131803-5803-1318
03-5803-131803-5803-1318

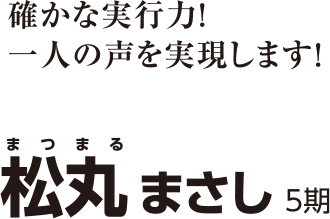
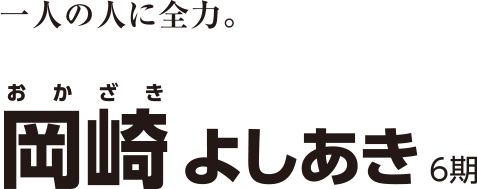

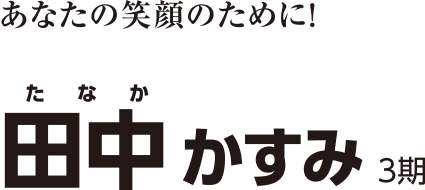
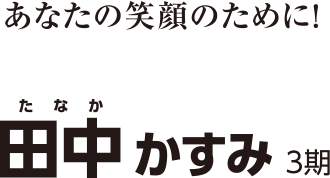


![]()
![]() 質問
質問
次に、災害対策についてお伺いいたします。
はじめに、避難所の環境改善についてお伺いいたします。
公明党としてこれまで避難所環境の改善について、TKB(トイレ、キッチン、ベッド)の迅速配備やスフィア基準の導入を訴えてきました。
政府は昨年12月に、避難所の運営指針を改定し、「スフィア基準」を取り入れ、それまでトイレは50人に1基だったものを20人に1基と明記し、トイレの比率を男性用と女性用を1対3とするよう推奨、入浴施設も50人に1つとの基準を示し、避難所内の一人当たりの居住スペースは「最低3.5平方メートル」を目指しますとしています。
また、昨年11月に中央防災会議等から「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について」の報告書が出され、その中で、国の応援組織の充実強化や、被災地のニーズに応じてキッチンカーやトイレトレーラー、ランドリーカー等を迅速に提供するための事前登録制度などを進めるとしています。
「スフィア基準」について、本区での避難所におけるトイレ基準の在り方、入浴施設の取り組みについて、そして避難所内の一人当たりのスペースについてご見解をお伺いいたします。本区では2次避難所の開設や、民間事業者等との協定締結などを進めてきましたが、実効性を高めるために福祉避難所以外の2次避難所などでの防災訓練の実施が必要と考えますが、お伺いいたします。
又、政府はキッチンカーやトイレトレーラー、ランドリーカー等の事前登録制度を検討していますが、本区ではどのように取り組むのかお伺いいたします。
東京都は首都直下地震等による被害想定等を踏まえ、災害時におけるトイレの環境向上を図ることを目的とし、「東京都トイレ防災マスタープラン」を策定しました。このプランと連動して区としてどのようにトイレ対策の強化に取り組むのか、ご見解をお伺いいたします。
本区としても「文京区トイレ防災マスタープラン」の策定を検討するべきと考えますが、ご見解をお伺いいたします。
又、今年度、本区では「避難所運営ガイドライン」の改訂をする予定となっておりますが、在宅避難をする方々への避難所での支援物資の配布についての計画が必要と思いますが、区のご見解をお伺いいたします。
次に、災害時における避難所等の通信確保についてお伺いいたします。
能登半島地震では、地中に埋設された光ケーブルなどの回線が断線するなどして、災害時の通信確保の課題が浮き彫りになりました。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなど各通信会社は、能登半島で様々な方法で通信を試み、その後も通信手段技術の強化に取り組んでいます。
「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について」の報告書では、実施すべき取組みとして、「衛星通信設備、公共安全モバイルシステム等の導入・活用及び速やかに使用できるよう平時からの訓練等について検討すべきである」としています。
避難所等の通信確保のため、衛星インターネット機器等の新技術の進展に応じた新しい通信サービス・機器について区として積極的な活用をするべきと考えますが、区のご見解をお伺いいたします。
この項の最後に大都市防災の課題解決についてお伺いいたします。
都市防災を専門とする東京大学の廣井悠教授は最近の著述の中で、大都市防災の焦点として、「激甚性」「複合性」「新規性」の3つをあげております。こうした課題に対応するために「インフラやハード設備に『余裕』や『冗長性』を意図的にどう設計および内生化できるかは大きな課題である」として、その課題解決の例として「防災とスポーツを組み合わせた『防災スポーツ』の取り組みを紹介しています。また、「緑に親しむ機能と避難場所機能を兼ね備えた『公園』などの事例」を紹介し、「防災対策の内容を防災のみならず多目的なものにすることで、余裕や冗長性を社会に意図的に設計することが可能」と述べております。
本区においても、このような発想で大都市防災の課題に取り組むことが有効であると考えます。地域住民の共助の取り組みを向上させるために、防災訓練を「防災スポーツ大会」とするなど検討してみてはいかがでしょうか、区のご見解を伺いいたします。
また、区の施設の再整備にあたっては、災害対策機能を内包していくことが有効と考えますが、ご見解をお伺いいたします。
|
区長 |
次に、災害対策に関するご質問にお答えします。 まず、避難所におけるスフィア基準についてのお尋ねですが、 令和6年能登半島地震を受け、国は、スフィア基準に基づく1人当たりの居住スペース等、避難所の環境改善に関する考え方を示すとともに、都においても、避難所運営指針を見直し、居住スペースや清潔なトイレ、入浴機会の確保等、誰もが不安やストレスなく安全に過ごせる避難所を目指すよう、方針を示したところです。 区としても、これらの考え方も踏まえ、今後、避難所運営ガイドラインを改訂し、避難所における生活環境の改善に努めてまいります。 次に、二次的な避難所についてのお尋ねですが、 区ではこれまでも、避難所に関する協定等締結団体と、二次的な避難所の開設・運用マニュアルを検討するなど、連携体制の強化に努めており、訓練の実施についても、今後、協議してまいります。 次に、災害対応車両登録制度についてのお尋ねですが、 国において、トイレ、調理などの機能を備えた災害対応車両の登録制度を今月から開始したところです。今後も、国の動向を注視しながら、登録を申請された車両の所有者等と、個別の調整に努めてまいります。 次に、トイレ対策についてのお尋ねですが、 都は、本年3月に「東京トイレ防災マスタープラン」を策定し、災害用トイレの整備により、空白エリアの解消や各施設におけるトイレの充足度の向上を目指すこととしております。区としても、都と連携しながら、区域の災害時のトイレの確保に努めてまいります。 また、区では、各避難所における携帯トイレの備蓄を進めるとともに、区有施設の改築等の機会を捉え、マンホールトイレの設置等に努めております。 なお、都の計画では、2030年度までに、区市町村において「災害時トイレ確保・管理計画」を策定することとしており、区としても、今後、災害用トイレの備蓄や整備について、課題を整理するとともに、計画の策定に向けた検討を行ってまいります。 次に、在宅避難者への支援物資についてのお尋ねですが、 現在、都において、在宅避難を含む避難者支援全体のあり方について検討が進められており、本年度中に、その考え方が示されると聞いております。 区としても、都の方針を踏まえ、避難所運営ガイドラインの改訂に合わせ、避難所における在宅避難者等に対する支援について検討してまいります。 次に、避難所等における通信環境の確保についてのお尋ねですが、 現在、区では、災害時における通信障害に備え、各避難所等に防災行政無線や災害時用の公衆Wi-Fi等を整備するとともに、防災センターに衛星通信機器を設置し、災害時の情報通信連絡体制の確保に努めております。 今後も、通信事業者による新技術の動向を注視しながら、災害時に有効な通信手段の導入について、研究してまいります。 次に、防災訓練についてのお尋ねですが、 これまでも、防災意識の高揚を図るため、町会・自治会対抗の「防災コンクール」を実施しており、本事業は、地域防災力の向上に加え、地域コミュニティの活性化にも資するものと認識しております。 区では、避難所総合訓練をはじめとする様々な訓練を実施しており、今後も、共助に基づく防災活動が活発に行われるよう、議員ご提案の考え方も含め、効果的な訓練内容を検討してまいります。 次に、区有施設の防災機能についてのお尋ねですが、 区有施設の再整備にあたっては、施設本来の用途を考慮しつつ、避難所等、災害時に求められる役割や地域の防災課題等に応じ、必要な防災機能の整備を検討しております。 引き続き、災害時の活用も想定した施設の再整備に努めてまいります。 |
|---|